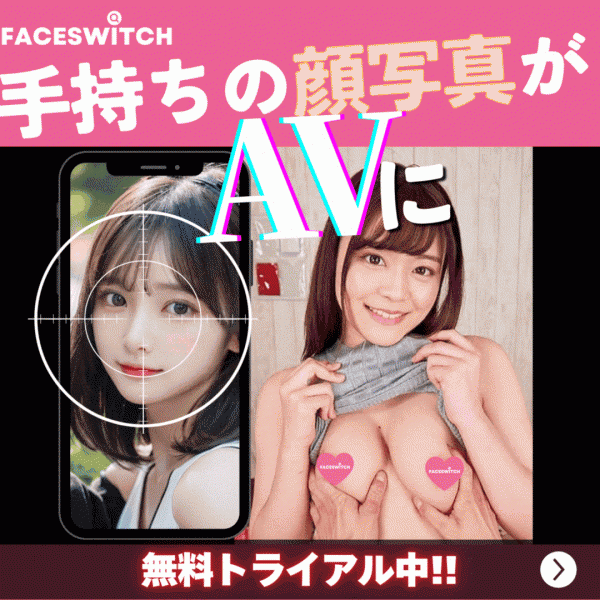レースクイーン ハイレグ問題 ハイレグは“時代遅れ”なのか──レースクイーン規制の波と日本モータースポーツ文化の現在地
かつて、サーキットの華と称されたレースクイーン。その象徴とも言えるのが、脚線美を強調するハイレグ衣装だった。1990年代から2000年代初頭にかけて、モータースポーツの現場では、ハイレグ姿のレースクイーンが当たり前のように存在し、レースの興奮に華を添えていた。
しかし、近年、その“象徴”に変化の波が押し寄せている。2020年代に入り、レースクイーンの衣装に対して“露出度の高いデザインを控えるように”という規制や自主的な見直しが進められているのだ。
今回は、この動きの背景と影響、そして日本のモータースポーツ文化におけるレースクイーンの役割について、じっくりと考えてみたい。
■ ハイレグ全盛期──“サーキットの女神たち”の時代
1990年代、F1ブームや全日本GT選手権(現・SUPER GT)の盛り上がりとともに、レースクイーンは一種の“アイドル的存在”として注目を集めていた。ハイレグ水着をベースにした衣装は、脚線美を強調し、サーキットに華やかさと非日常感をもたらしていた。
当時は、レースクイーンの写真集やビデオが飛ぶように売れ、テレビや雑誌にも多数登場。モータースポーツファンのみならず、一般層にもその存在は広く知られていた。
ハイレグは、単なる露出ではなく、“戦う男たちを応援する女性たちの象徴”として、ある種の美意識やスタイルを体現していたとも言える。
■ 規制の背景──時代の価値観とメディアの変化
しかし、時代は変わった。2010年代以降、社会全体で“ジェンダー平等”や“性的表現の見直し”が進む中、レースクイーンの衣装にも批判の目が向けられるようになった。
特に、SNSの普及により、サーキットで撮影された写真が瞬時に拡散されるようになったことで、「子どもも来場するイベントで過度な露出は不適切ではないか」という声が高まった。
また、スポンサー企業のイメージ戦略も変化。企業の社会的責任(CSR)やコンプライアンスが重視される中で、「過度な性的アピールはブランドイメージにそぐわない」と判断するケースも増えている。
その結果、SUPER GTやスーパーフォーミュラなどの主要レースでは、主催者やチームがレースクイーンの衣装に一定のガイドラインを設けるようになり、ハイレグや極端な露出を控える傾向が強まっている。
■ ファンの声──“文化”としてのレースクイーン
こうした動きに対して、ファンの間では賛否が分かれている。
「時代の流れとして仕方がない」「女性の尊厳を守るためには必要な変化だ」と理解を示す声がある一方で、「レースクイーン文化を否定するのは寂しい」「ハイレグは芸術性やスタイルの表現だった」といった意見も根強い。
特に、長年モータースポーツを応援してきた世代にとっては、レースクイーンの存在は単なる“お色気”ではなく、レースの一部であり、サーキットの風景そのものだった。
■ 海外との比較──“自由”と“配慮”のバランス
興味深いのは、海外のモータースポーツ界でも同様の議論が起きていることだ。F1では2018年に“グリッドガール”の廃止が発表され、賛否両論を巻き起こした。MotoGPやインディカーでも、女性の起用方法や衣装について見直しが進んでいる。
一方で、ヨーロッパや南米の一部では、伝統的な衣装や演出を残しつつ、女性の主体性や表現の自由を尊重する形で継続している例もある。
つまり、“露出=悪”という単純な構図ではなく、“誰のための表現か”“どのような文脈で行われているか”という視点が、今後ますます重要になっていくのだろう。
■ これからのレースクイーン像とは?
では、これからのレースクイーンはどうあるべきなのか。
一つの方向性として、“応援する女性”から“発信する女性”への進化が挙げられる。実際、近年ではSNSを活用して自ら情報を発信し、ファンとの交流を深めるレースクイーンが増えている。衣装も、露出よりもスタイリッシュさや個性を重視したデザインが主流になりつつある。
また、モータースポーツの魅力を伝える“アンバサダー”として、レースの知識やトーク力を活かして活動するレースクイーンも登場している。これは、単なる“見られる存在”から、“伝える存在”への進化とも言えるだろう。
■ 最後に──“ハイレグ”が語る時代の記憶
レースクイーンのハイレグ衣装に規制がかかるというニュースは、単なる服装の話ではない。それは、時代の価値観の変化、メディアの進化、そして社会全体の“まなざし”の変化を象徴する出来事だ。
だが同時に、あのハイレグ姿に熱狂し、カメラを向け、サーキットに通った日々を覚えている人々にとって、それは“青春の記憶”でもある。
文化は変わる。だが、かつての風景を懐かしむことは、決して悪いことではない。むしろ、それを知っている世代だからこそ、これからのレースクイーン文化をどう育てていくか、考えることができるのではないだろうか。